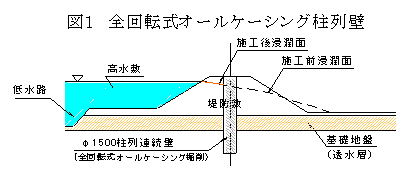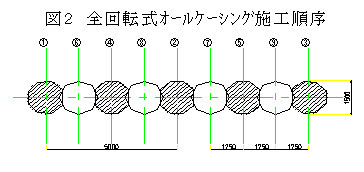|
��36��@�Z�p�m�S�����i���j ���ȉ�e�[�}�F��S�@�u�Z�p�̃}�l�[�W�����g�v �_���^�C�g���F�s�s��h�̌���h�~�� �@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@��@�ܘY �ߔN�s�s�́A�n���X�A�n���S�A�r�����̒n�������i�݁A��͐�̒�h�������V�`�X���ƂȂ��Ă���B��h�̌���́A�_���̌����Ôg�ɕC�G����B�^���̒n���ւ̗����́A�Q�ƂȂ��ė���Ă�����̂����ݍ��݁A�P�X�X�X�N�ɔ������������n�����Q����r�ɂȂ�Ȃ��ɂȂ�B�Q�S���Ԋ�������n���X�A������������̏Z��X�A�������g���H�A����Ԃ̏a�A�L�͈͂̊����Ől���ړ��ł��Ȃ����A���Њ����́A���܂�ɂ����G�ł���B�n��̊����A�ݔ��A�P���́A���R�K�v�ł���B����ƕ��s���āA����قǐl�����W�����A�������ɊJ������A�n���ւ̖h�����̗L���A�����A���x�ƃn�U�[�h�}�b�v�̊����[������v���Ȃ����A���ɉ���D�悷�ׂ����ł���B ���y��ʏȂ́A�͐��h�̒������ʂ��Q�O�O�U�N�x���Łu�����Ǘ������h�̓��A�v�捂���ʂ܂ő�������ƂR�V�����Z������̊댯��������B�v�i�z������A��@����ΏۊO�j�Ɣ��\�����B�ȏ�܂��A�V������h����h�~�H�@���Љ��B �@��h����h�~�H�@�i���āj �P�D�Z�p�T�v ��̐c�ɋ��x�Ɛ[���ƎՐ����̂���A�������ǂ��Z�����g���Ǔy�Œz������B �Q�D�T�v�@ ���݉͐��̒��S����V�[��萂���ɑS��]���I�[���P�[�V���O�Ō@�킵�A�P�[�V���O���Ɍ@��y�𗘗p�����Z�����g���Ǒ̂�Ő݂��Ď������̍����n���A������ǂ����A�Ր����Ɛ��ɑ��ċ��x�̂����̂�B �R�D���e�i�}�P�A�}�Q�j �@�@�S��]���I�[���P�[�V���O��1500���g�p����B �A�@���lj~�`�P�������b�v�����邱�ƂŘA���ǂ�z������B �B�@���Ǒ̂́A�������Ɋ�b�n�Ղ���p�C�s���O�E�{�C�����O�̔������Ȃ������Ƃ���B �C�@���Ǒ̂́A���x���Q�`�T�m�^mm2���x�ɃR���g���[�����A�n�������ʼn��Ǎނ��g�U�E�������ɂ����z���Ƃ���B
�S�D���� �@�@�S��]���I�[���P�[�V���O�́A�n����Q���i�ʐA�]�A�̐A���j�ɑΉ��ł��A�A�������n���ǂ��z���ł���B �A�@�@��y��j�ӁE���x�������ĉ��Ǒ̂Ɏg�p���A�c�y�̔�����}����B �B�@���Ǒ̂̋��x���Q�`�TN�^mm2���x�ɃR���g���[�����邱�Ƃɂ��A�{�H�̔\���A��Ɛ������߁A�⋭�A��C�A�p���������\�ɂ���B �C�@�Ր����������B�i���Ǒ̂́A�s�����܂�Y�����A�I�[���P�[�V���O�ɂ��A�ʼn�����O�̒n�������ɂ����Ǎނ̊g�U�E������h�~�ł���B�j �D�@�����ł��ψ�Ȓn���ǂ�z���ł���B�i�@��y�A�Z�����g�A�Y���܁A���̔z�����Ǘ����ăZ�����g������������Ǒ̂����A�g���~�[�ǂɂ��Ő݂���B�������˝��a���ǁA���a���A�I�[�K���ɂ��n���A���ǂ́A���Ǎނ̊g�U�A�푖�A�ʐE�]�E�̐E���ؓ��n����Q���A�@��ǖʕ��ɂ��i�����s�ψ�ƂȂ�B�j �E�@���͒n�Ղ��ɂ߂Ȃ��B�i���Ǒ̂�Ő݂��Ȃ���P�[�V���O�����Ƃ�����͒n�Ղƈ�̂ƂȂ�A�ɂ܂Ȃ��B�j �F�@����̒�̓V�[�ō�Ƃ��ł���B�i�S��]���̋@�B�����́A�R�`�S���ƒႭ�A�@�B����3.6�`4.3m�ł���B�j �G�@�X�[�p�[��h�ɔ�ׂčH��������B�i�X�[�p�[��h�̍H����́A�Q�O�O�S�N�܂łɊ������������S�Vkm�ő��z�S��X�S���~�A�P�疜�~�^m�|�����Ă���B����́A�Q�`�R�疜�~�^m�|����ƍl������B���H�@�͂P�T�O���~�^m�ȉ��ł���B�j �T�D���� �@�@��h�p�n�̊g������������Ȃ��B�i�Ր��ɂ���̂̐Z���ʂ��オ��Ȃ��̂ŐZ�����ɂ��@�K�����h���A�@�K�i�ǂ̒z���E���グ�◠�@�ʂ��}���z�ɂł��A��̂̐��グ���\�ł���B�j �A�@�������̐Z���A�y�щz���ɂ���h����ɒ�R�ł���B �Z ���A������ǂɂ͋��x�Ǝ�����������A�ݗ��̒�h�̌���̂悤�ɒ�̕����������Đ�@���H�A���x�ƂȂ�Ȃ��B �Z ��̂̎Ր��ɂ��A���݂����ǂ��A�^�������ɔ툳���ꂽ�Z�����Ɖz�����̍����ɂ���ĒZ���ԂɌ���̂�h�����Ƃ��ł���B �Z ��b�n�Ղ̎Ր��ɂ��A�����w����^�������ɔ툳���ꂽ�n�������Ɖz�����̍����ɂ��Z���ԂɌ���̂�h�����Ƃ��ł���B �B�@����ŘA���Ɏ{�H���\�ŃX�[�p�[��h�i�����܂łɌ���̐i���ł́A���S�N������B�j�̂悤�ɖ��{�H���̌���ɑ����_������Ȃ��B �C�@���O�������قƂ�ǂ���Ȃ��B�i�S��]���I�[���P�[�V���O�́A�n����Q���ɋ����A���A�]�A�ʐɉe������Ȃ��j �U�D�l�@ ��h�́A���J�ɂ�茈����̂��Ƃ����l������ʓI�ł���B ��̂ɐc�����茈�Ă���̂̍�����1/2���c���Ă���A�y���E�w�h���̒���n�ւ̗��������Ȃ��Ȃ�A�^����ɒZ���ԂŒ�����ʂ������邱�Ƃ��\�ŁA�Z���Ԃł̒�h�������\�ƂȂ�B �n���P�[���u�J�g���[�i�v�ɂ��ЊQ�i���҂P�R�O�O�l�ȏ�A���Q��Q�O���~�j�̂悤�ɐ����A���\���A�Ƃ���������ƉƉ��͎g���Ȃ��Ȃ�A�C���t���������Ԓ�~����B�u�a�̌������������B�v�i�킸���Ȗ��f��s���ӂ��厖���������Ƃ�����B�j�̂��Ƃ��̗l�ɓs�s�͐�̒�h�́A�z���̗������Â��A�����̒����A�������\�����ł���A���̈ꕔ�Ɍ��ׂ������Ă����A��Q���g�傷��B���Ɏア�y����h�̌��ׂ́A��ɕω����A�����璲�����s���Ă��T���o������̂ł͂Ȃ��B�Ǘ����ꂽ���x�̂���A�������\�����i�Ր��ǁj�Ƃ���K�v������B �V�D������ �ߋE�̑�a��ł́A�Q�O�O�V�N�V���P�V���~�J�O���̉e���ŏW�����J���������A�v�捂���ʂ��Ă���B���J���Z���Ԃł��������Ƃ����Q�́A�قƂ�ǔ������Ȃ��������X�ɂQ�`�R���Ԃ������ǂ��Ȃ��Ă�����������Ȃ��ł������B �s�s�͐��h�́A����̓��H�A��n�A�H�ꓙ�̊J���ɂ�闬�o�W���̑����◬�B���Ԃ̒Z�k�A�n�����g���ɂ��䕗�̑�^����W�����J���X�̌����Ō��A�s�s�����v����댯���������Ȃ��Ă���B ���́A�@�B������Ă��Ȃ�����̉͐�@�����i�P�X�U�S�N�j�́u��̍ޗ��͓y���v����������A��h�����̋������l���Ă��Ȃ��B �͐�w�̐搶�����ł������Ȃ��u�X�[�p�[��h���̍�����Ⴍ����B�z���⋭��h�E�V���n��݂���B�v�����咣���Ă���B ���Ђւ̋ߓ��́A�i�������H�@�Œ�h���������邱�Ƃ����i���j�ł͂Ȃ��A�Љ�i���j�ɑi������@�����Ȃ��B ���N�P���ɂm�g�j�́A��h�̉t��̓V�X�e���𓌋��d�C��w���J�����A�Q�d�ɍ|���Ő݂��邱�Ƃ��L���ł���ƕ��������B ��w�ɘA�������A��͂����肢�������y�̐�傪���Ȃ��ƒf���ꂽ�B�y�،������̓y���E�U���`�[���ɂ���Ă������i��ł��Ȃ��B���̂悤�ȋZ�p�𑁊��ɐi�W������ׂɂ́A�l�łȂ�����ɂ킽�镔��������{�Z�p�m��̉��f�I�Ȋ����ɂ��u�Z�p���}�l�[�W�����g����B�v���K�v�ƍl����B ���ӌ������҂����Ă��܂��B |
�@�@�@�@�@�@�@��@�@�܁@�Y
�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�@�Z�p�m�i���݁^�����Z�p�ė�����j
�@�@�@�@�@�@�@�@�@E-mail�@:
mine-5556@nifty.com